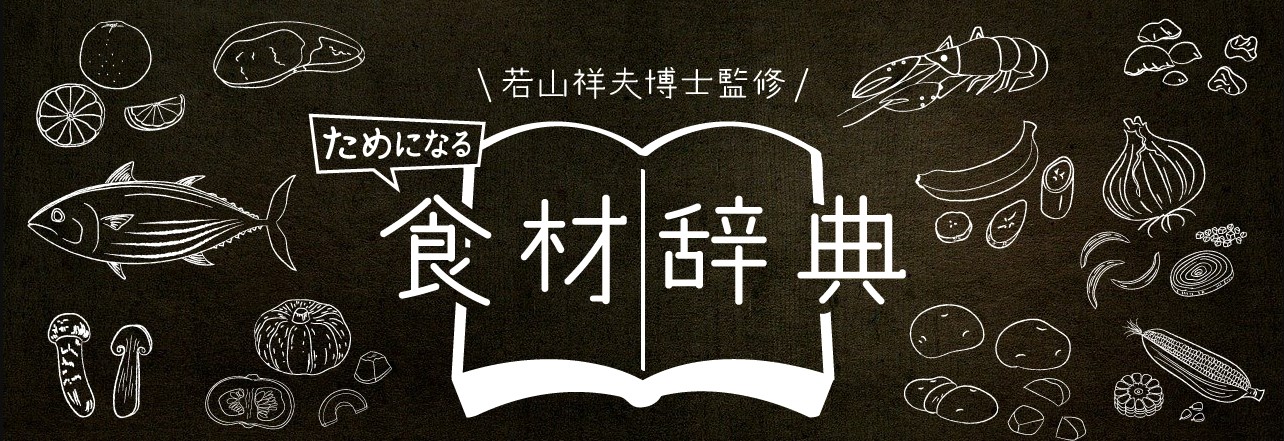産地と属性
日本で古くから飲まれている甘味飲料で、原料として米と米麹から作られるものと、酒粕から作られるものに大別される。「酒」と名がつくが、市販されているものの多くはアルコールをほとんど含まない(1%未満)ため、ソフトドリンクに分類される。
米麹と米を原料とする甘酒は、粥状にした米に米麹を入れて一晩寝かせることでデンプンが糖化して甘くなる。「一夜酒」とも呼ばれるのはこのためで、正月に寺社などで振舞われるものの多くはこの製法で作られたもの。
一方、酒粕を原料とするものは、湯の中に酒粕を入れて溶かし、砂糖などを加えて甘くする。
甘酒には下記のように様々な栄養素が含まれており、特にブドウ糖が豊富なため「飲む点滴」と称されることもある。また、現代では寒い時期に飲むものとのイメージを持たれているが、江戸時代、おもに暑い時期の夏バテ防止用として飲まれていたのは、そういった理由による。(俳句では夏の季語にされている)
栄養成分の働き
脳の栄養素としてよく知られているブドウ糖は、血糖値を上げ脳の満腹中枢を刺激するため、食前に飲むことで食事量を減らすことができるだけでなく、食後の血糖値上昇を抑えることにもつながるため、ダイエットに適しているとされる。
ビタミンB群には、たんぱく質の代謝を助ける作用があるため、肌や髪の調子を整える効果が期待できる。
麹菌は免疫力を高める働きがあるため、疲労回復や風邪の予防に効果が期待できる。
食物繊維やオリゴ糖は、腸内環境を整え、便秘解消などにも役立つ。
栄養成分
炭水化物(デンプン)、たんぱく質、ビタミンB1・B2、葉酸、カルシウム、リン、亜鉛、銅、食物繊維など
注意点
酒粕を原料として作られた甘酒には、酒粕に少量のアルコール分が含まれていることがあるため、酔うことがある。飲料時には注意が必要。
ポイント
栄養素を豊富に含む甘酒だが、カロリーも高いため、量を考えて飲むようにしたい。
夏に熱い甘酒を飲むときには、すりおろしたショウガを加えるとサッパリと飲むことができる。