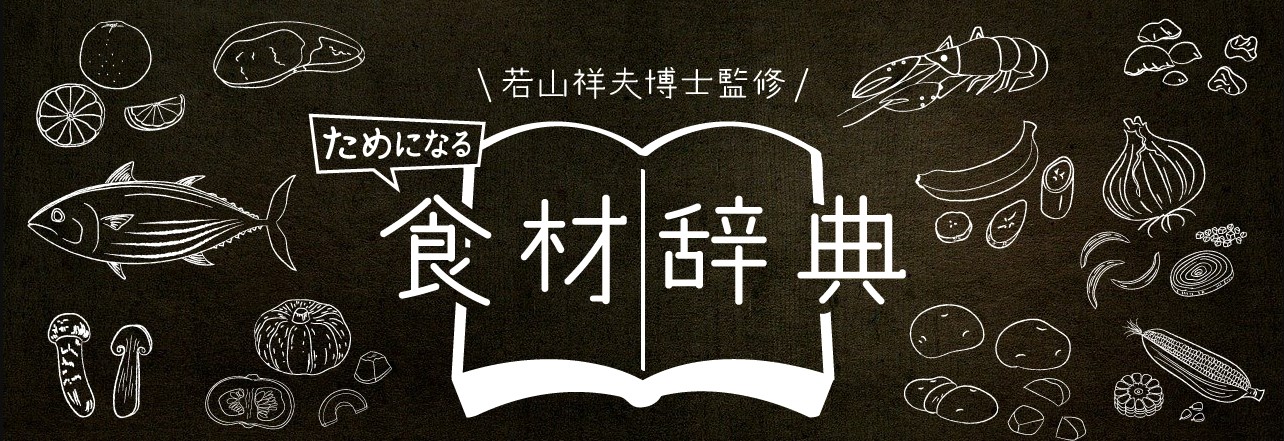産地と属性
緑茶を炒って(焙煎して)淹れた日本茶のこと。「ほうじ(焙じ)」とは乾炒りの意味で、家庭で作る場合は、「焙じ炉(ほうじろ)」または「焙烙(ほうらく・ほうろく)」と呼ばれる道具が使われた。
以前はどの家庭でも日常的にほうじ茶を作り飲んでいたが、これは古くなって鮮度が落ちた緑茶の茶葉を美味しく飲むための手段でもあった。
焙ずることで苦味成分であるタンニンが壊れ、渋味や苦味が抑えられる。さっぱりとした口あたりがあり、誰でも飲みやすいのはこのため。また、煎茶にくらべて含まれるカフェイン量が少ないため、多量でなければ就寝前などでも飲むことができる。
近年はペットボトル飲料としてコンビニなどで売られているほか、ラテやアイスクリームなどスイーツの材料としても注目されている
栄養成分の働き
ポリフェノールの一種であるカテキン類は、血中のコレステロールを低下させるほか、抗酸化作用や脂肪の燃焼を促進する作用があるため、生活習慣病の予防に効果が期待できる。
焙じることで生まれる香り成分のピラジンは、血行促進や心身をリラックスさせる効果がある。
また、アミノ酸の一種であるテアニンにもリラックス効果があり、睡眠を促したり、緊張を緩和するなどの効果がある。
栄養成分
カテキン類、ピラジン類、テアニンなど
注意点
酸化による変色が少ないため、淹れた後も長く持つように思いがちだが、含まれているたんぱく質が腐敗して変質する。腐敗したほうじ茶を飲むと、下痢や嘔吐を引き起こすため、注意すること。
ポイント
家庭で作る場合は、専用の道具がなくても、フライパンを使って緑茶が赤茶色になるまで乾炒りすればできる。また、ほうじ茶ラテやほうじ茶アイスを作る場合は、粉状になったほうじ茶パウダーが売られているので、それらを使うと良い。